母集団形成
大企業採用担当者が直面する壁と突破口
採用活動の出発点となる「母集団形成」。
求人広告やナビサイトを使えば応募は集まるものの、「欲しい人材」に届かない。
数は多いのに参加率が低く、歩留まりも悪い。
そんな悩みは規模に関わらず多くの採用担当者が直面しています。
母集団形成の本当の課題は「数が足りない」ことではなく、
「質をどう高めるか」「温度をどう保つか」にあります。
本記事では、悩みの構造、背景、原因、そして解決の方向性を整理します。
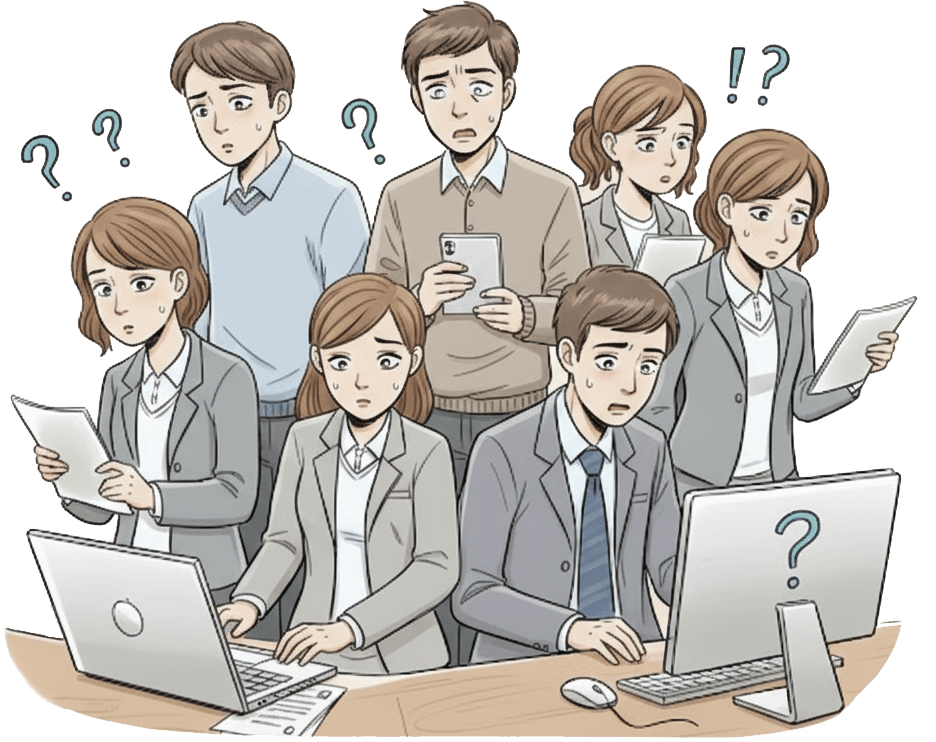
よくあるお悩み
- エントリー数は確保できるが、ターゲット層からの応募が少ない
- 説明会の参加率が低く、広告コストが無駄になっているい
- ナビサイト中心で、他のチャネルを活用できていない
- SNSやダイレクト採用に挑戦したいがノウハウが不足している
- 内定辞退が多く、初期の母集団に無駄が発生している
「数が多いから安心」という時代は終わり、むしろ数が多すぎて“質の低下”や“歩留まり悪化”に直面しています。
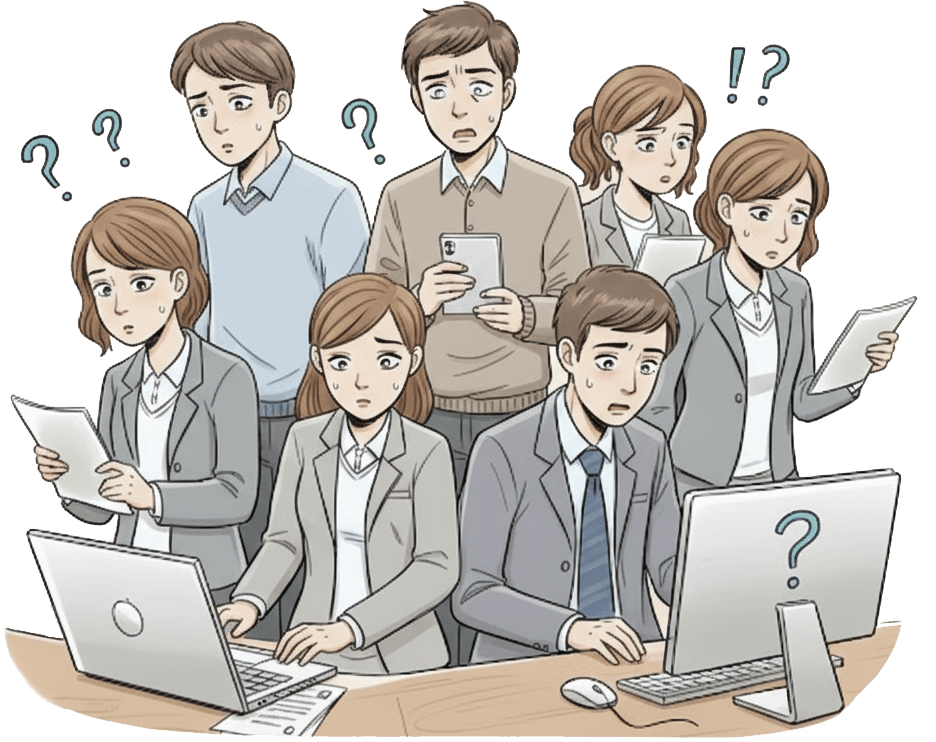
背景にある構造的な要因
学生の就職活動スタイルの多様化
かつてはナビサイト一強で、掲載企業は自動的に母集団を確保できました。しかし現在はSNSやオウンドメディア、スカウト型サービスなど、学生が企業に出会う経路が分散。大企業も「待っているだけ」では本命層を取り逃します。
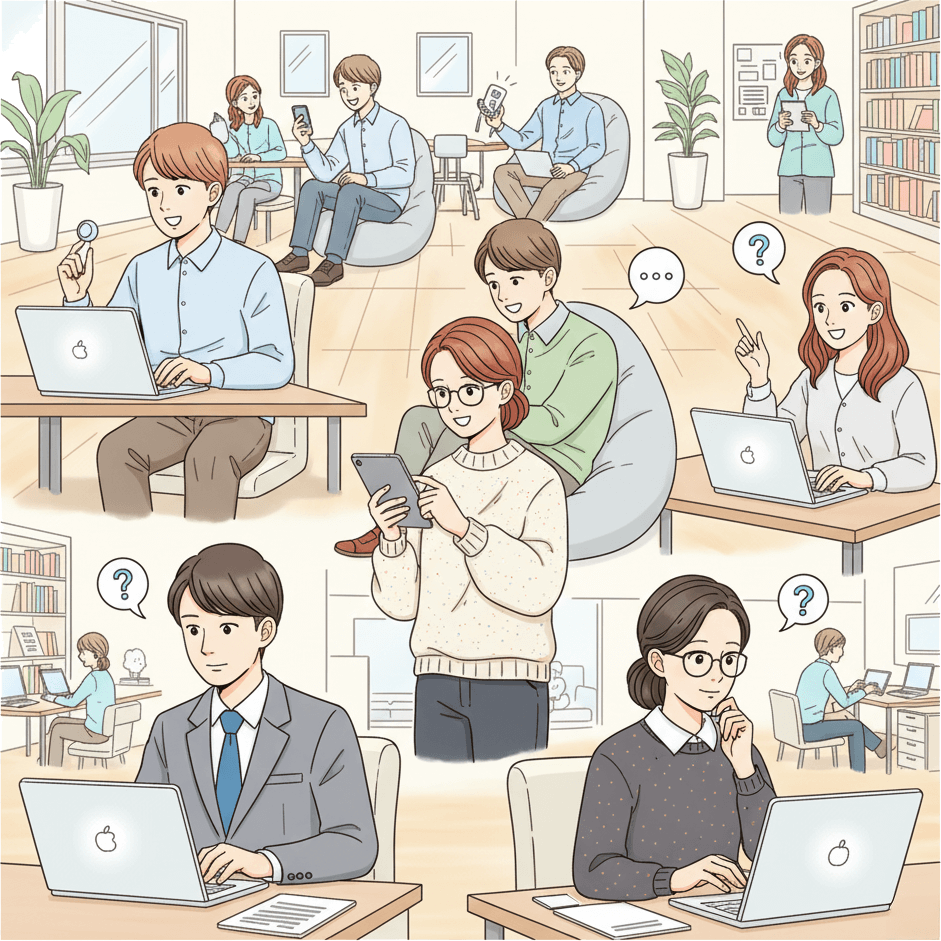
情報の飽和と差別化困難
多くの企業が「成長できる」「風通しが良い」といった抽象的なメッセージを発信しています。結果として候補者には違いが伝わらず、知名度だけでは志望度につながりにくい状況が生まれています。
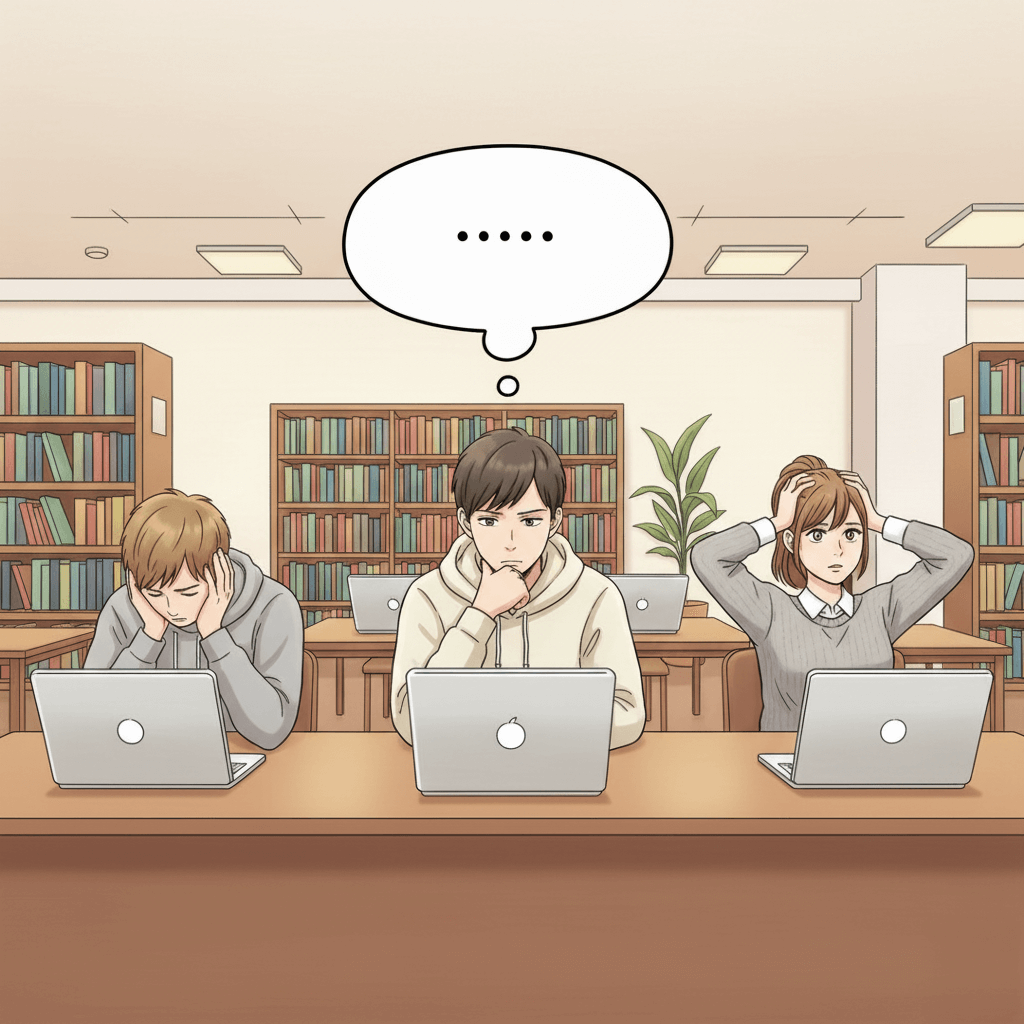
志望度の低下
エントリーは「とりあえず応募」のケースも多く、応募者の志望度は年々低下。説明会や面接に進むまでに熱が冷めやすい状況があります。
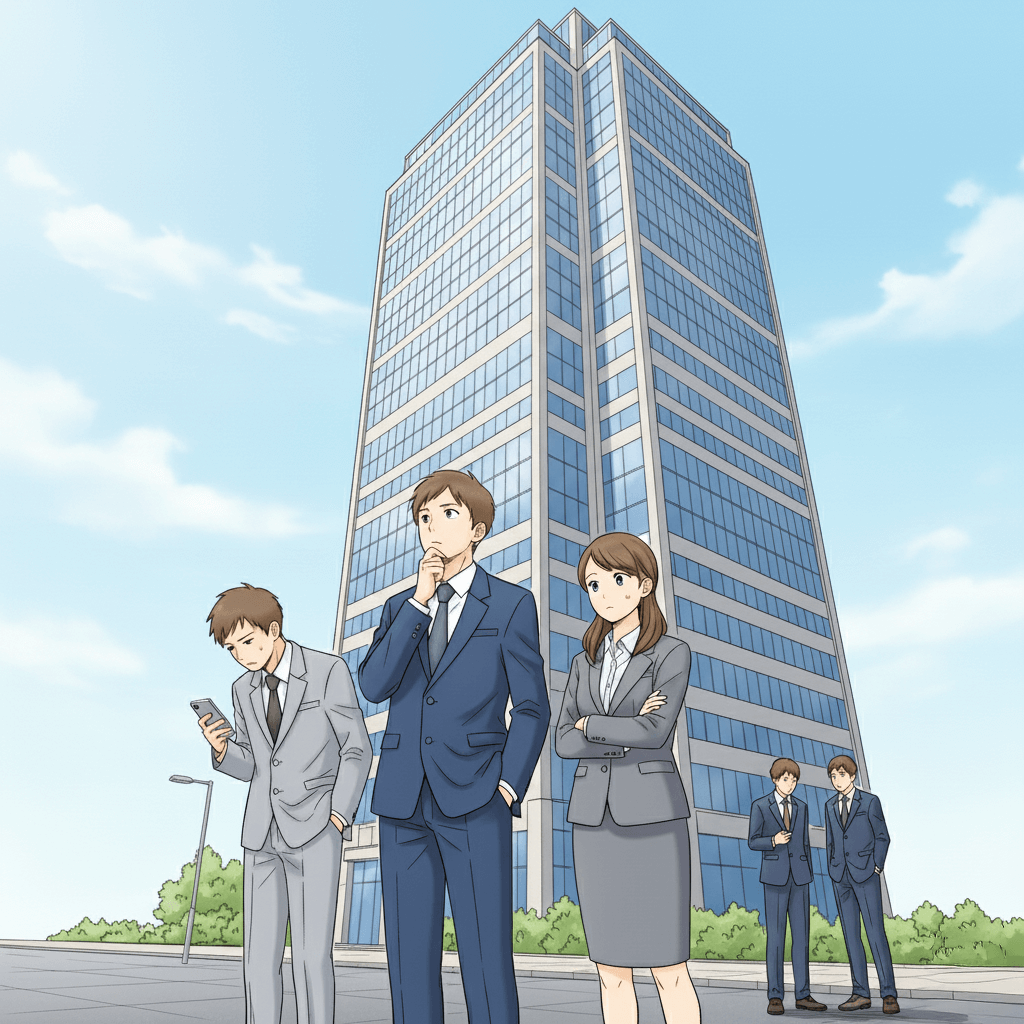
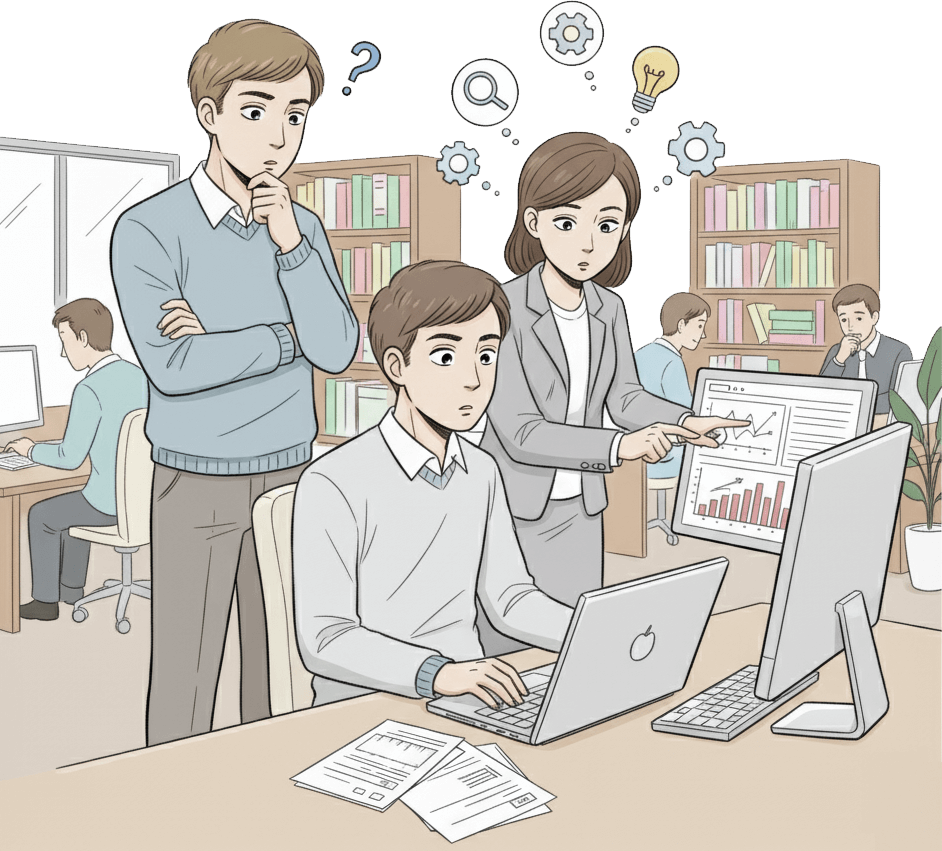
原因を整理する
- 量と質のギャップ:エントリーは集まるがターゲットから外れる人も多い
- 接点設計の弱さ:エントリー後のフォロー不足で歩留まりが悪化
- チャネル戦略の偏り:ナビサイト頼りで、新しい方法に踏み出せていない
- データ不足:チャネル別の効果を可視化できず、改善が進まない など
「数が多いから安心」という時代は終わり、数が多すぎて“質の低下”や“歩留まり悪化”に直面。
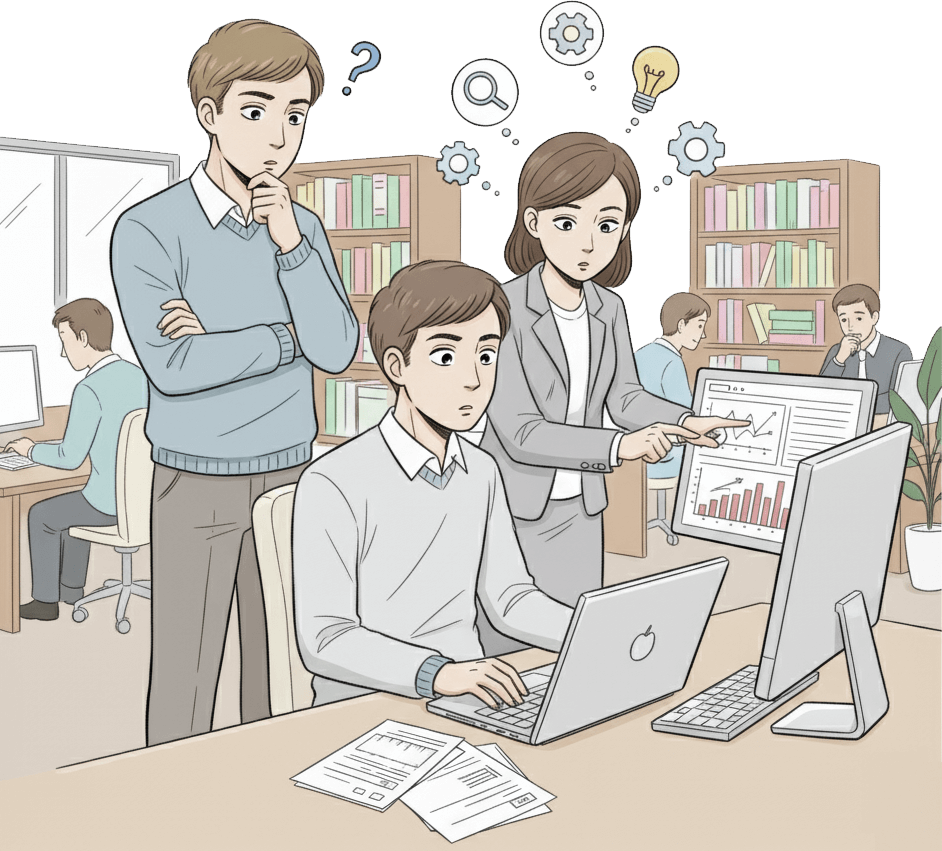
解決の方向性と打ち手
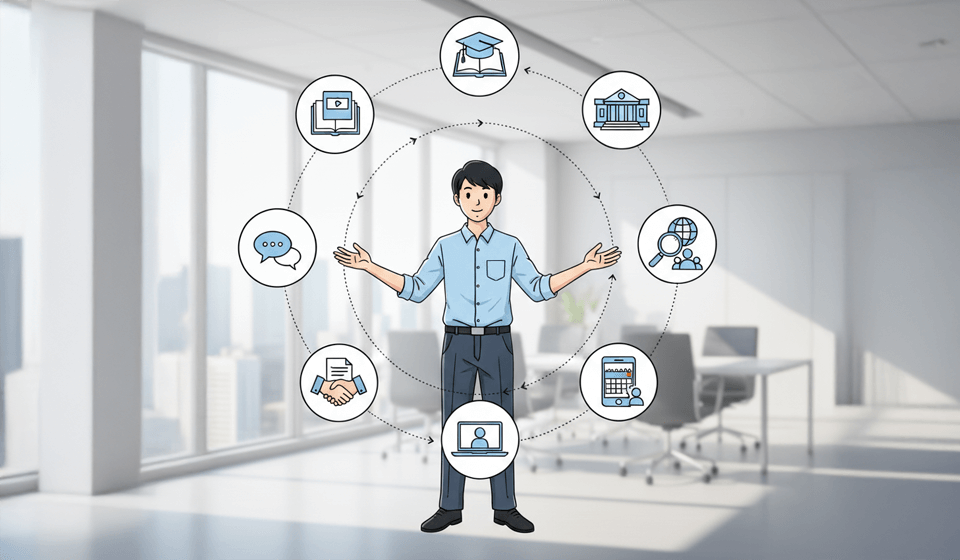
1. チャネルの多角化
ナビサイトを主軸にしつつも、スカウト・SNS・リファラルを並行活用することで、ターゲット層との接点を増やす。特にスカウトは質の向上、リファラルは志望度の高さにつながります。
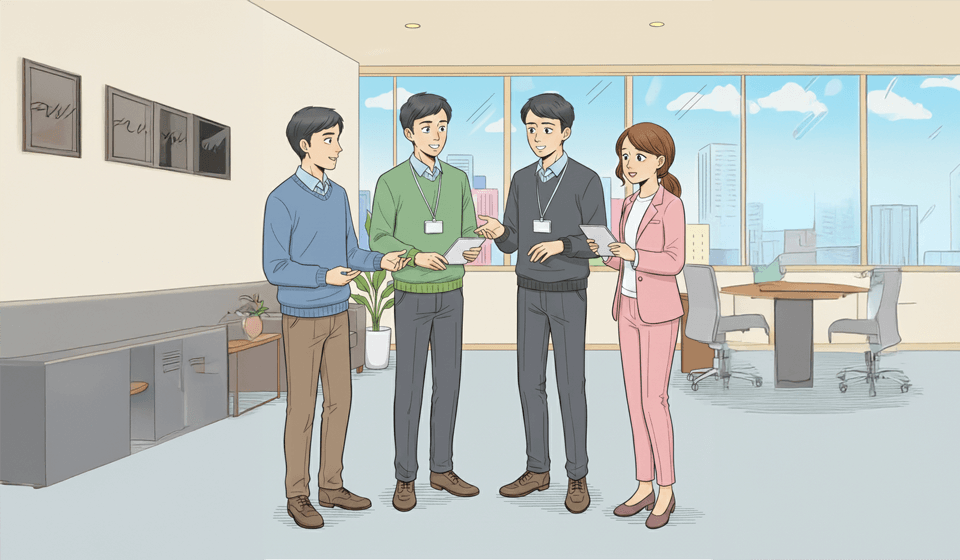
2. エントリー後の接触強化
サンクスメールや限定動画、LINEなどを活用し、候補者の温度を冷まさない。説明会案内を個別化するだけでも歩留まりは改善します。
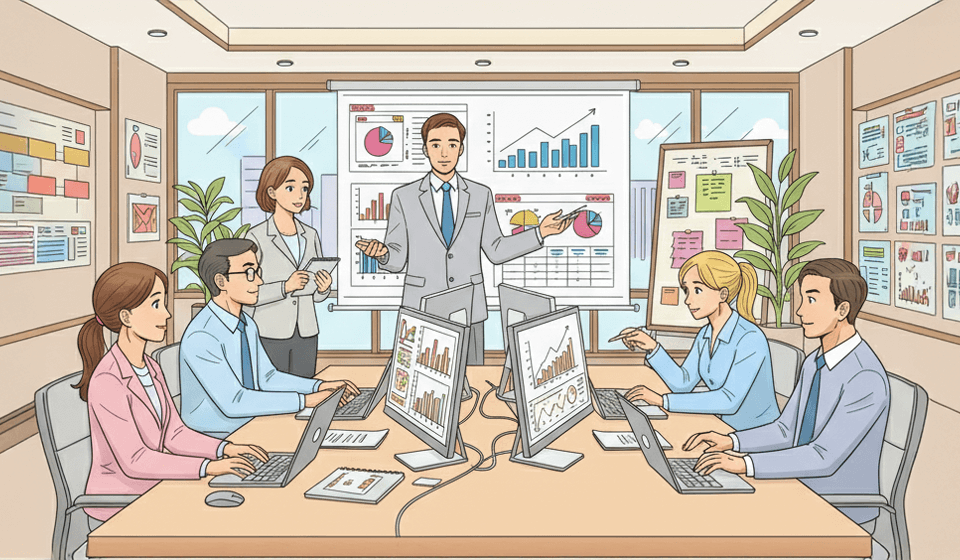
3. ブランドメッセージの再定義
「大きな会社」ではなく「なぜこの会社なのか」を伝えるメッセージ設計が重要です。社員インタビューや具体的な数字を使い、“等身大の会社像”を示しましょう。
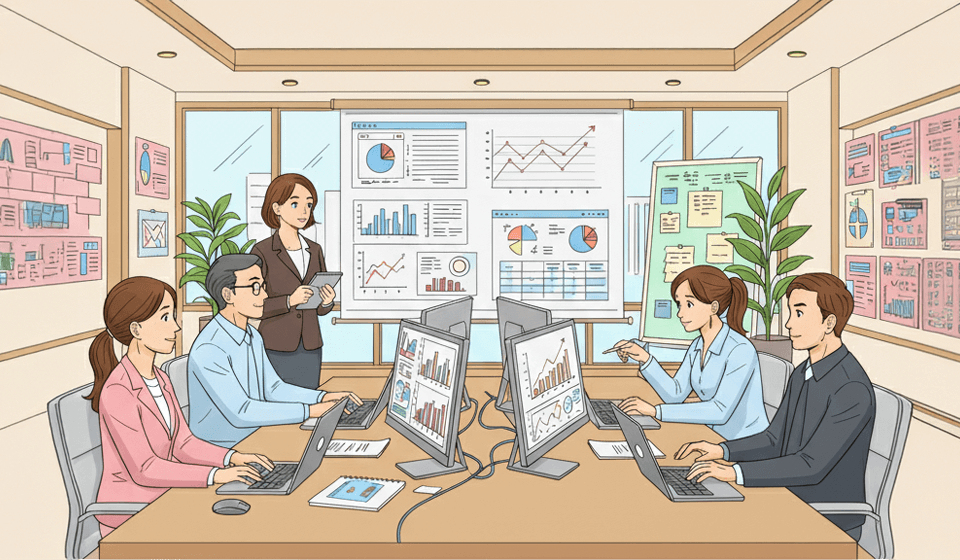
4. データ活用による改善
参加率・キャンセル率・内定承諾率などを指標化し、チャネルや施策ごとにPDCAを回す。属人的な経験則から脱却し、科学的な改善を実現します。

