選考プロセス
公平性と納得感を両立する仕組みづくり
「面接官によって評価がばらつく」
「候補者から“何を見られているかわからない”と不安の声が出る」
「選考に時間がかかり、途中で辞退されてしまう」
選考プロセスの設計は、採用活動における核心部分です。
ここが整っていないと、せっかく母集団を形成しても、
途中で候補者が離脱したり、入社後のミスマッチにつながったりします。
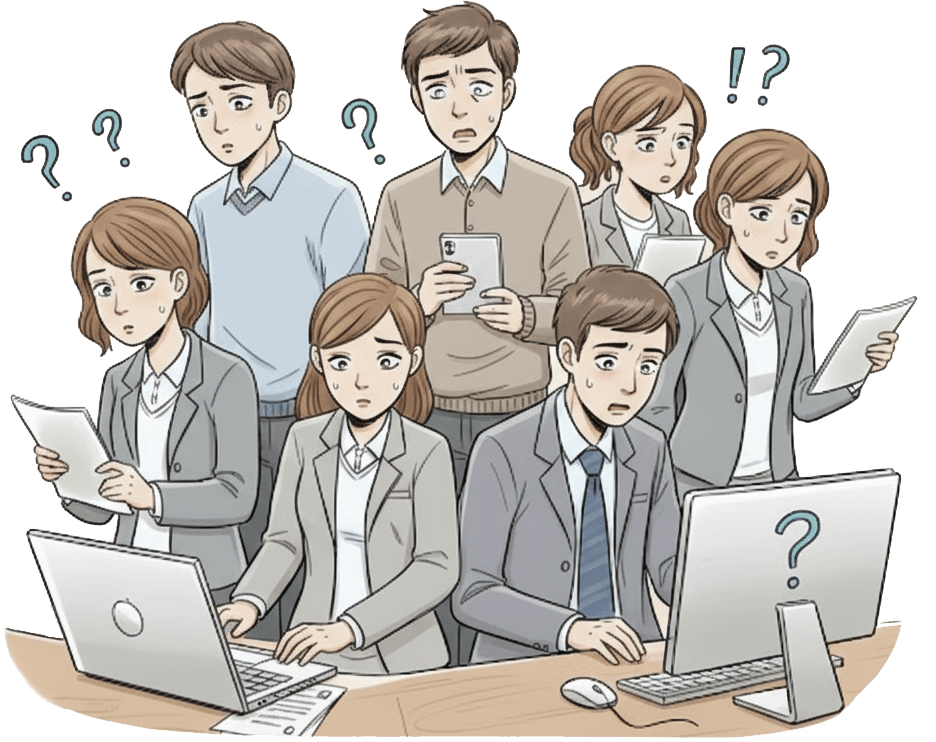
よくあるお悩み
- 面接官ごとに質問内容や評価基準がバラバラ
- 選考フローが長く、候補者の熱が冷める
- 候補者から「不透明でわかりにくい」と言われる
- 一貫性のない評価で内定辞退や早期離職が発生
- 選考官の準備不足で印象が悪くなる
知名度や事業規模に関わらず、「魅力はあるのに伝わらない」という課題は、多くの企業に共通しています。
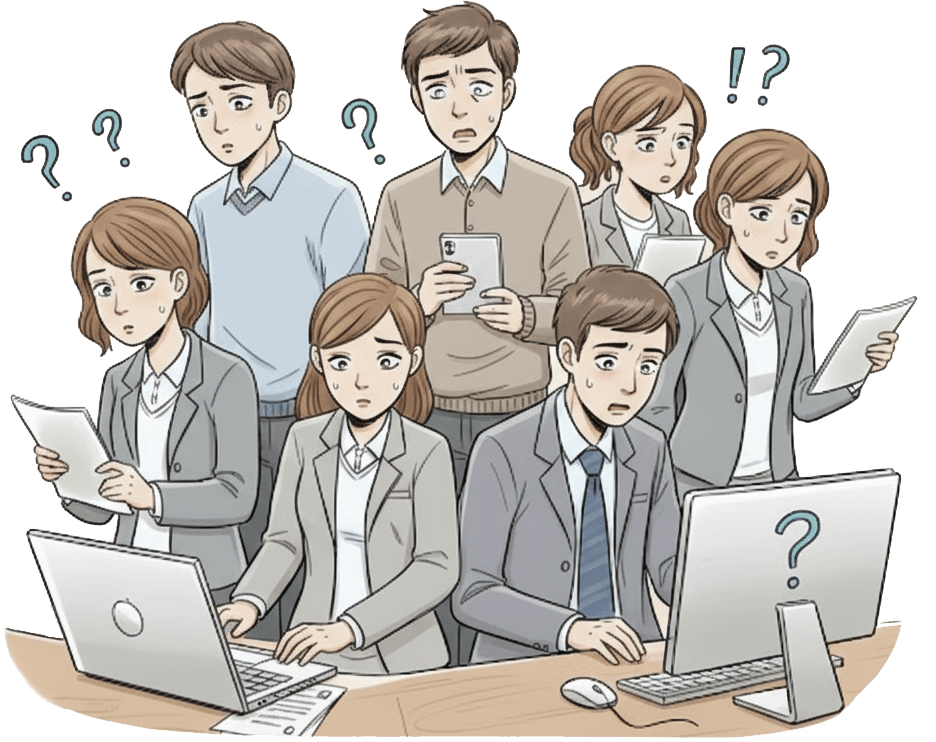
背景にある構造的な要因
01
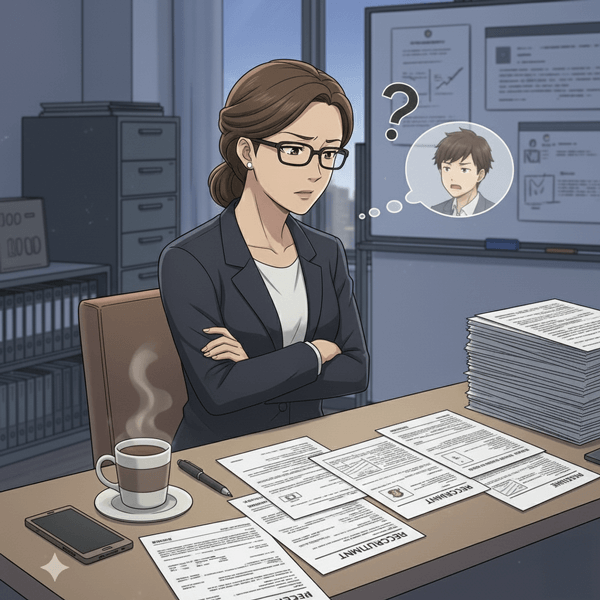
評価基準の属人化
面接官の経験や価値観に依存し、同じ候補者でも評価が変わってしまう。
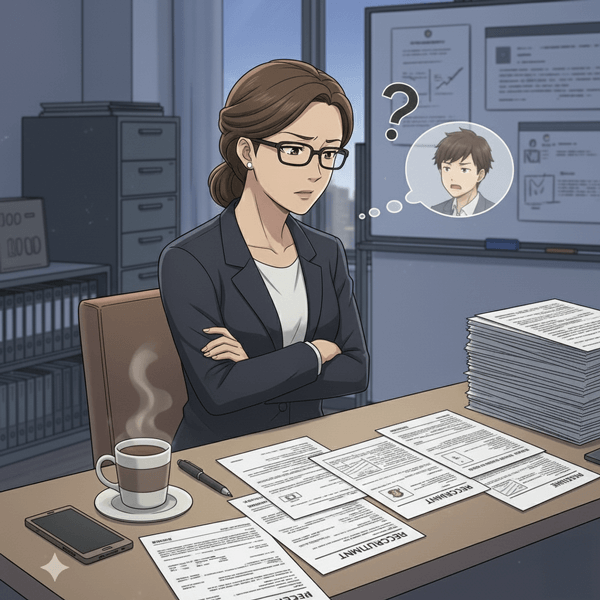
02
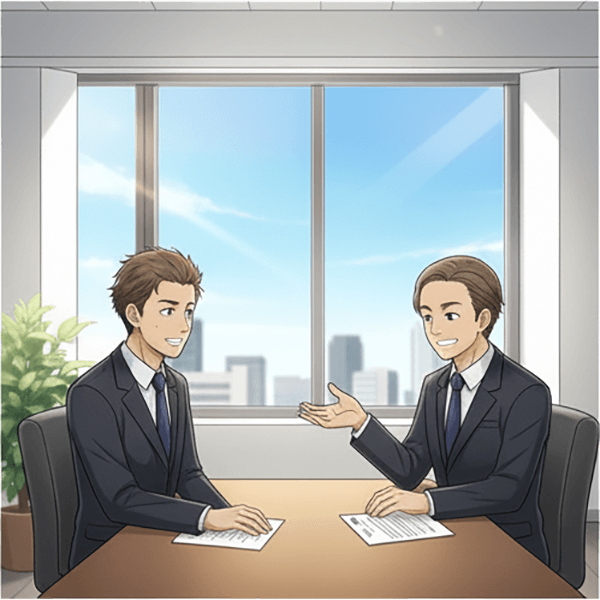
選考設計の形骸化
「昔からこのフローだから」という理由で、今の候補者に合わないやり方を続けている。
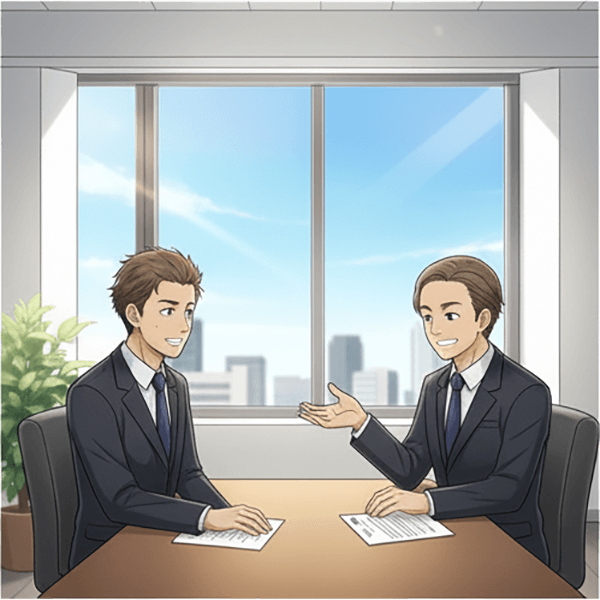
03
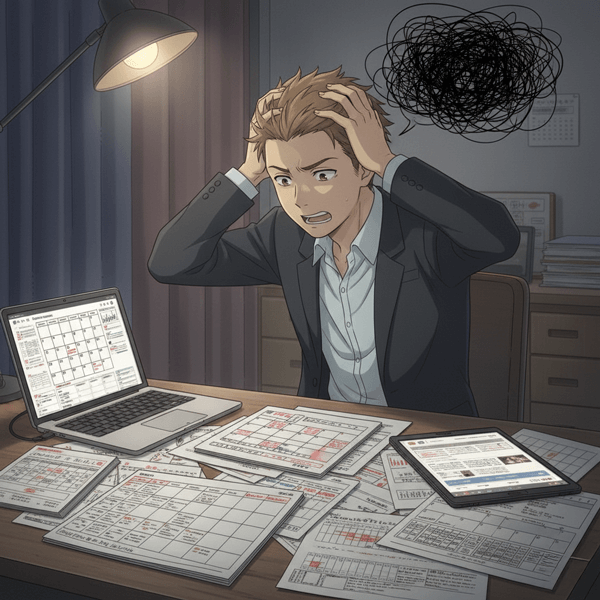
候補者体験の軽視
企業側の都合で面接回数や日程が組まれ、候補者の利便性や心理的安心が欠けている。
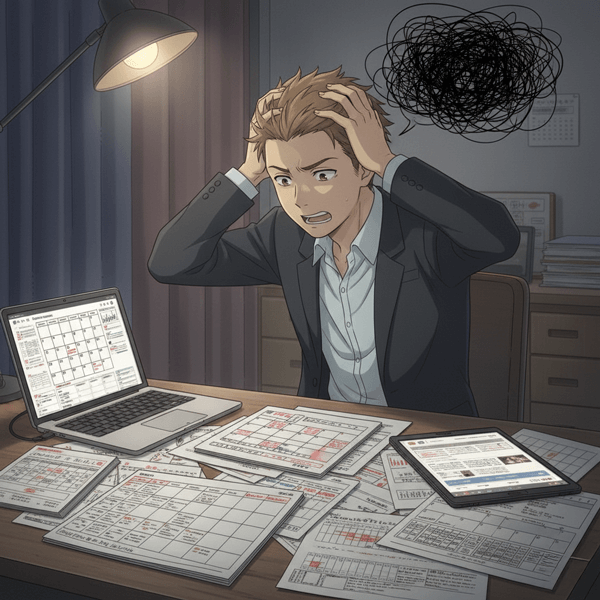
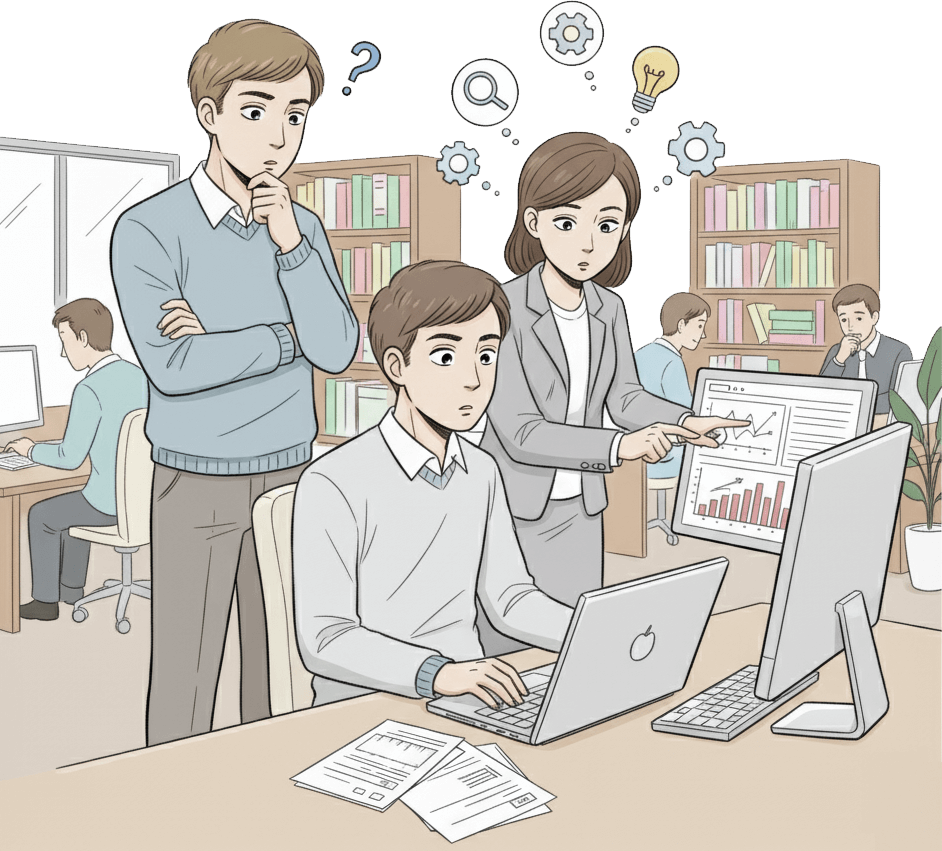
原因を整理する
- 評価の不統一:採用基準が曖昧で、面接官に周知されていない
- プロセスの長期化:複数回面接・調整の遅れで候補者の温度が下がる
- コミュニケーション不足:候補者へのフィードバックがなく不信感を招く
- 面接官教育の不足:面接のスキルや質問設計が体系化されていない
「数が多いから安心」という時代は終わり、数が多すぎて“質の低下”や“歩留まり悪化”に直面。
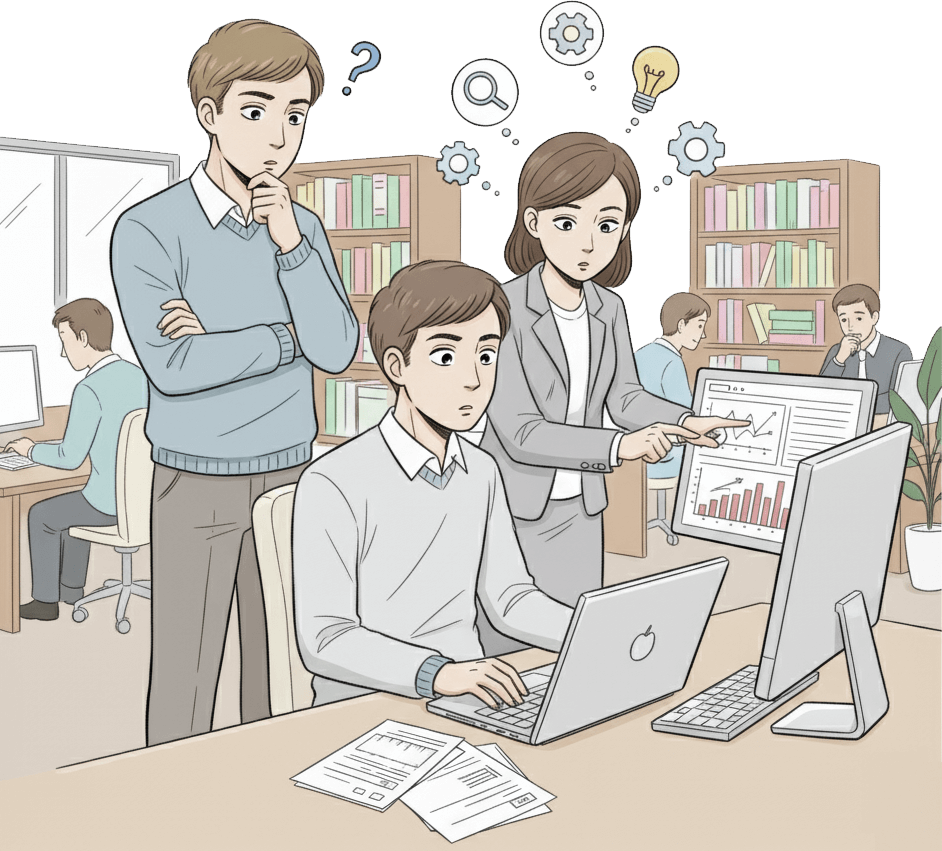
解決の方向性と打ち手
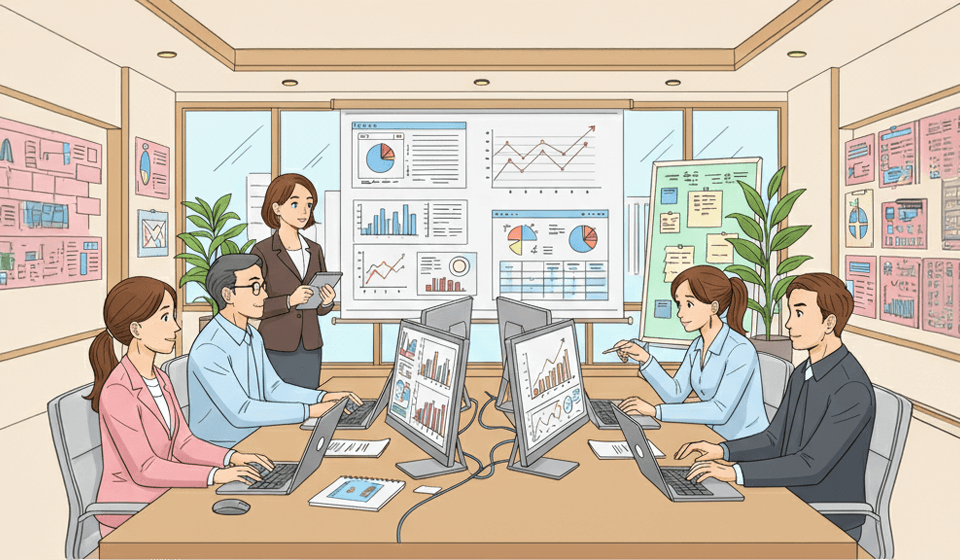
1. 採用基準の明文化と共有
「スキル」「マインド」「ポテンシャル」など評価項目を明確に定義し、面接官全員が同じ基準で判断できるようにする。
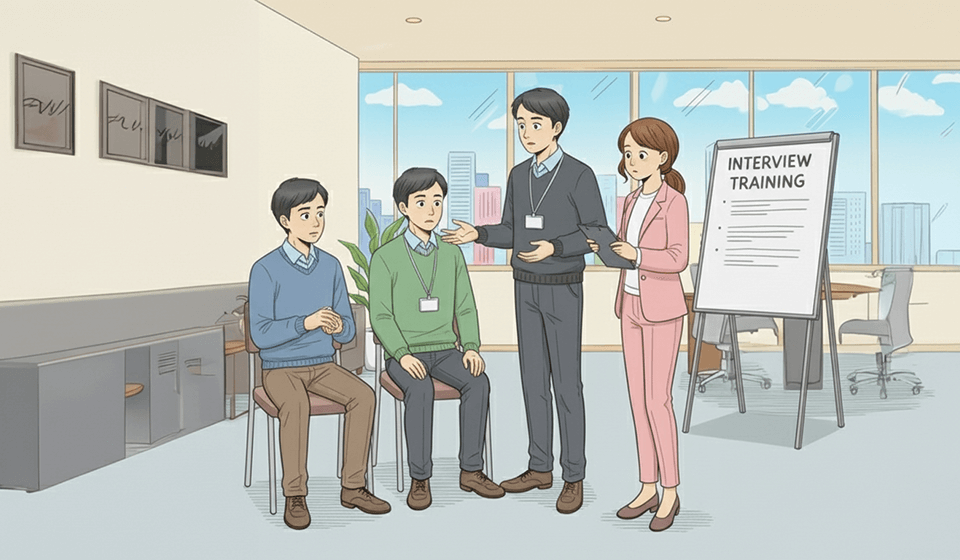
2. 面接官トレーニング
質問リストの標準化、バイアス理解、評価ワークショップなどを実施。属人的な判断を減らし、公平性を高める。
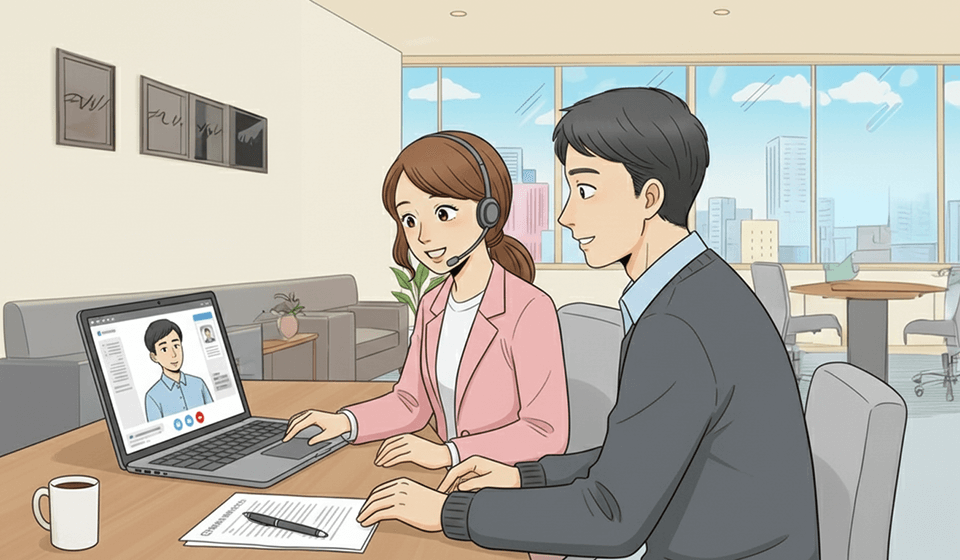
3. プロセス短縮とスピード感
一次面接をオンライン化する、日程調整ツールを導入するなどで時間を短縮し、候補者の熱を逃さない。
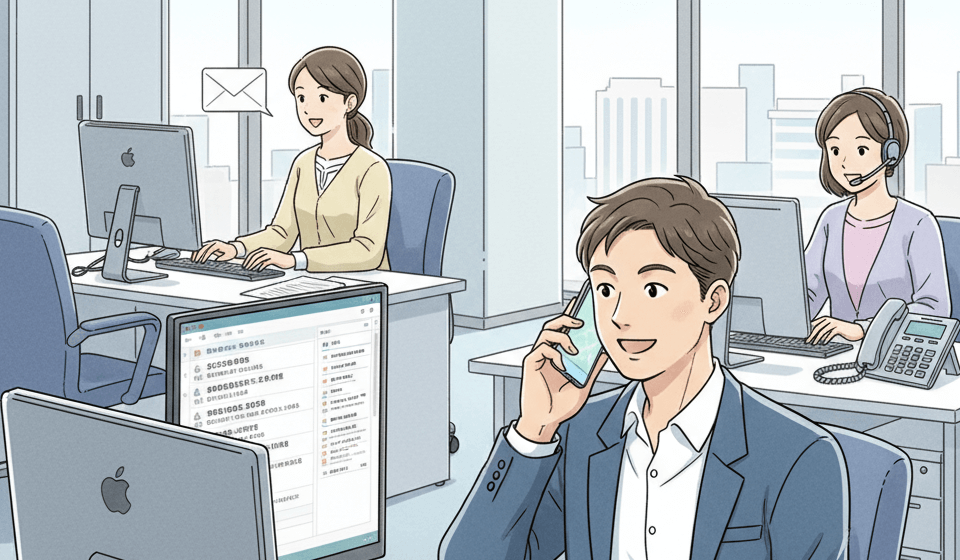
4. 候補者体験の向上
選考中のこまめな連絡、面接官の準備徹底、結果連絡の迅速化など、候補者が「大切にされている」と感じる仕組みを組み込む。
選考プロセスの打ち手例
「候補者体験は、もはや隠せない。面接官の些細な一言、連絡の少しの遅れが、口コミサイトやSNSで、一気に拡散される。一つのミスが、会社の評判を地に落とす”命取り”になりかねない…」 まるで、ミシュランの星付きレストランで、 […]
「『何か質問は?』と聞くと、『特にありません』と返ってくる。その無気力さに、こちらのモチベーションまで削がれていく…」 面接の最後に、渾身の力で投げかけたキャッチボールの球が、ぽとりと地面に落ちるかのような、あの虚無感。 […]
「面接のドタキャン、サイレント辞退が本当に多い。学生からの連絡一本で済む話なのに…」 「確保した役員や現場社員の時間と労力を考えると、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになる。」 その罪悪感は、採用担当者としての責任感の強 […]
「早期離職者が出ると、『一体どんな人材を採用したんだ』と経営陣からも現場からも責められる。まるで、全ての責任を押し付けられたようで…辛すぎる。」 手塩にかけて採用した人材が、志半ばで去っていく悲しみ。そして、それに追い打 […]
「面接官からのフィードバックが『コミュニケーション能力に課題あり』だけ。具体的に何を見てそう判断したのかが全く分からない…」 まるで暗号のような、抽象的すぎるフィードバック。それを次の面接官に申し送ることもできず、結果と […]
「アイスブレイクで雑談をしたら、『本題に入ってください』というオーラを出された。ただの評価者と被評価者でしかないのが悲しい。」 この問題の本質は、採用担当者が「良かれ」と思って行うアイスブレイクと、学生が「これも評価のう […]

